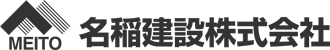- HOME
- コラム
コラム
-
ライフ・パートナーズ vol.63
- 投稿日

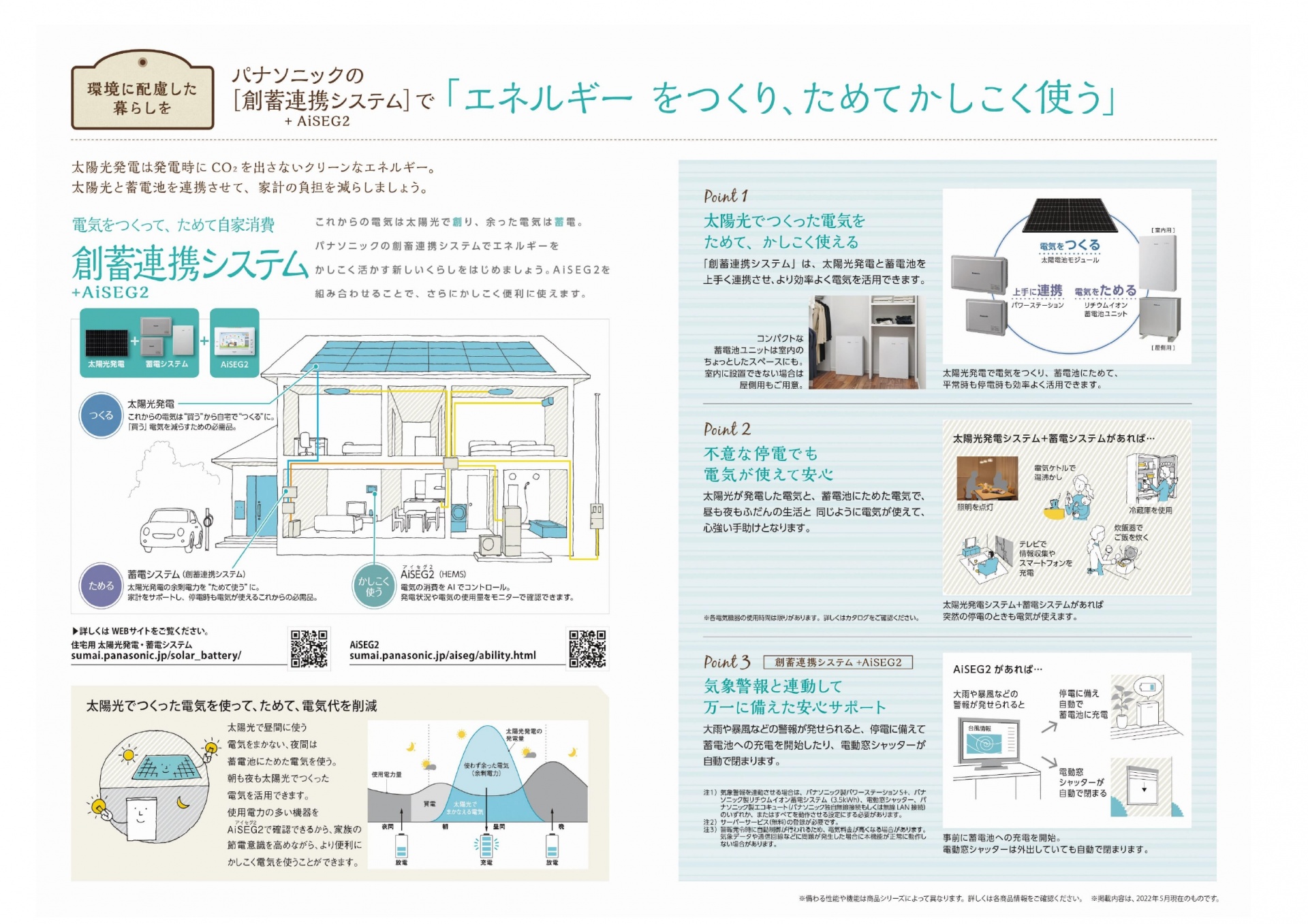
-
ベランダ(バルコニー)は「なくてもいい派」が増えている?その理由を解説します
- 投稿日
こんにちは!名稲建設株式会社です。
最近はマイホームを建てる際「ベランダ(バルコニー)」を作らないお客様が増えています。少し前までは「あるのが当たり前」という感もあった住まいのベランダ(バルコニー)。
なぜ、今設置しない家が増えているのでしょうか。家づくりのプロの視点から、その理由を解説します。▶︎ベランダ(バルコニー)は掃除が大変!?
ベランダ(バルコニー)は屋外にあるため、雨やほこりで汚れやすい場所。また、鳥がフンを落としたり、近くの木々から飛んできた枯れ葉が溜まって排水溝を塞いでしまったりすることも、可能性としてはゼロではありません。

もちろん、こまめに掃除すれば新築時の綺麗な状態を保てますが、掃除が面倒というご家庭がほとんどでしょう。
毎日目につくところならまだしも、日頃目につく場所ではないのでベランダ(バルコニー)を頻繁に掃除するのは家事負担が増えると感じることもあるという理由から、「作らない」という選択をされる方も少なくありません。▶︎そもそもベランダ(バルコニー)に洗濯物を干さない

最近は共働きで日中家にいないご家庭や、外に干すと花粉や黄砂、PM2.5などが気になるという理由から室内干しをするご家庭が増えています。
洗濯が終わったらそのまま乾燥機で乾燥させたり、家の中に専用のスペースを設けて干したりするライフスタイルの場合。ベランダ(バルコニー)に洗濯物を干すこともないので、「いらないかも」と感じることも。
布団も同様で、外に干さずに布団乾燥機を使用するご家庭が増えています。▶︎建築コストやメンテナンス費用がかかる

ベランダ(バルコニー)を設置すると、定期的にベランダ(バルコニー)の床を防水のための塗り替えする必要が出てきます。
広さにもよりますが、だいたいベランダ(バルコニー)の塗り替え費用は6~10万円程度。外壁塗装と比べれば費用はもちろん少額ですが、もし日頃使っていないのであれば、これだけのメンテナンス費用が定期的に必要になるのはちょっとした負担に。また、建築時にもベランダ(バルコニー)を造る費用がかかります。もしベランダ(バルコニー)を造る分の費用を他の場所に回せるなら。という理由で、作らない方もいらっしゃいます。
今日はベランダ(バルコニー)を作らない方がどうして「作らない」という選択をされているのか、その理由をいくつかご紹介してみました。
もちろん!洗濯物は外干し派の方や、ベランダ(バルコニー)でのんびり過ごしたいという方にとって、ベランダ(バルコニー)空間はとっても便利な場所。
ライフスタイルやマイホームでどんな暮らしをしたいかに合わせて、自分たちにあった選択をしてみるのが一番です。どうしようかな、と迷ったら、お気軽にご相談くださいね◎ -
「こどもみらい住宅支援事業」解説!vol.2〜手続・ポイント・2022年4月28日発表の交付申請期限等の延長について編〜
- 投稿日
こんにちは!名稲建設株式会社です。今日は、先日こちらのコラムでもご紹介させていただいた「こどもみらい住宅支援事業」に関して、マイホームを建てる際に役立つ実際の手続きやポイントについて解説させていただきます。また、2022年4月28日に国交省より交付申請期限等の延長についても発表されましたので、その辺りもご紹介いたします。▶︎おさらい:こどもみらい住宅支援事業とは? 2021年11月末に閣議決定され、すでにスタートしている「こどもみらい住宅支援事業」。「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や省エネ改修」に対する補助金事業として、これから家を購入される方も大いに使える制度となっています。給付の対象となるのは、新築の場合18歳未満の子どもを持つ子育て世帯や、夫婦どちらかが39歳以下の若者夫婦世帯。リフォームに関しては給付対象となる工事を実施していれば、子育て世帯であるか、若者夫婦世帯であるか否かに関わらず、全世帯で申請できます。<対象や金額に関して詳しくはこちらの記事を参考に>[事業公式サイト]こどもみらい住宅支援事業▶︎こどもみらい住宅支援事業の具体的な手続
2021年11月末に閣議決定され、すでにスタートしている「こどもみらい住宅支援事業」。「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や省エネ改修」に対する補助金事業として、これから家を購入される方も大いに使える制度となっています。給付の対象となるのは、新築の場合18歳未満の子どもを持つ子育て世帯や、夫婦どちらかが39歳以下の若者夫婦世帯。リフォームに関しては給付対象となる工事を実施していれば、子育て世帯であるか、若者夫婦世帯であるか否かに関わらず、全世帯で申請できます。<対象や金額に関して詳しくはこちらの記事を参考に>[事業公式サイト]こどもみらい住宅支援事業▶︎こどもみらい住宅支援事業の具体的な手続 では実際に、「こどもみらい住宅支援事業」を活用するためには、一体どんな手続きをすれば良いのでしょうか?手続きに関しては、前回ご案内した通り、家を新築された方が何か申請するということはありません。この事業の交付申請等のすべての手続きは、新築住宅の建築事業者が、こどもみらい住宅支援事業事務局が提供するWebシステム上で行います。ここからは、新築でマイホームを建てる場合の手続きを1つ1つご説明していきます。(1)共同事業実施規約の締結最初から、なんだか難しい言葉が並びますが、「共同事業実施規約」とは、事業の対象となる家を建てる建築事業者と、補助金を受け取る対象者(お施主様)との間で、補助金交付後の還元方法を決めること。この事業は、補助金を一旦建築事業者が代表として受け取り、お施主様に還元します。そのため、交付申請をする前にきちんと「どのタイミングで、どんな方法で」お施主様に補助金を還元するかを決めておかなければいけません。(2)交付申請の予約次に必要となるのが、交付申請の予約です。こちらは任意となりますが、「こどもみらい住宅支援事業」は予算が限られている補助金事業です。そのため、予算がなくなれば新規の受付をストップする可能性も大いにあり得ます。そうなる前に補助金の交付申請の予約をすることも可能です。予約の有効期限内は予算が確保されるので、確実に受け取りたいという方は、予約をしていた方が安心です。<交付申請の予約期間>2022年3月28日~遅くとも2023年2月28日*期限は4月28日の発表により今年9月末から2023年2月28日へと延長となりました。 予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合は、同日まで。(3)交付申請新築住宅の建築工事に着手し、出来高の工事完了の確認を持って「こどもみらい住宅支援事業」の補助金交付申請手続きをします。申請期間は、4月28日の発表により今年10月末から2023年3月31日まで延長となりました。交付申請の締め切りは、補助金を申請する人が多く予算上限に達すれば、2023年3月31日より早まる可能性もあります。(4)交付決定申請した内容が確認されたら、何も問題がなければ1ヶ月半〜2ヶ月ほどで交付が決定します。決定したら『交付決定通知書』というものが発行され、建築事業者の担当者にメールで通知されます。また、家を建てた建築主(お施主様)のもとにも交付決定を通知する書類が郵送されてきます。(5)補助金の確定・交付交付が決定した後は、対象となる補助金が家を建てた住宅会社の元へと振り込まれます。振込の時期は次の①②のいずれか。どちらか早い方になります。① 2022年10月末までに交付申請を行う場合、2022年度末(2023年3月末ごろ振込)、2022年11月以降に交付申請を行う場合、2023年度末(2024年3月末ごろ振込)② 完了報告の審査完了(当月20日締、翌月末支払予定)ここで気を付けておきたいのが、補助金は一旦建築工事を行なった会社の元に振り込まれる点です。還元方法は、最初に取り交わす「共同事業実施規約」で決めておくこととなりますので、しっかり内容を把握しておきましょう。(6)完了報告完了報告の期限までに新築住宅の引渡しと入居を受け、完了報告をすることとなります。戸建住宅の場合、完了報告の期限は4月28日の発表により2023年5月31日から2023年10月31日まで延長となりました。▶︎こどもみらい住宅支援事業のポイント
では実際に、「こどもみらい住宅支援事業」を活用するためには、一体どんな手続きをすれば良いのでしょうか?手続きに関しては、前回ご案内した通り、家を新築された方が何か申請するということはありません。この事業の交付申請等のすべての手続きは、新築住宅の建築事業者が、こどもみらい住宅支援事業事務局が提供するWebシステム上で行います。ここからは、新築でマイホームを建てる場合の手続きを1つ1つご説明していきます。(1)共同事業実施規約の締結最初から、なんだか難しい言葉が並びますが、「共同事業実施規約」とは、事業の対象となる家を建てる建築事業者と、補助金を受け取る対象者(お施主様)との間で、補助金交付後の還元方法を決めること。この事業は、補助金を一旦建築事業者が代表として受け取り、お施主様に還元します。そのため、交付申請をする前にきちんと「どのタイミングで、どんな方法で」お施主様に補助金を還元するかを決めておかなければいけません。(2)交付申請の予約次に必要となるのが、交付申請の予約です。こちらは任意となりますが、「こどもみらい住宅支援事業」は予算が限られている補助金事業です。そのため、予算がなくなれば新規の受付をストップする可能性も大いにあり得ます。そうなる前に補助金の交付申請の予約をすることも可能です。予約の有効期限内は予算が確保されるので、確実に受け取りたいという方は、予約をしていた方が安心です。<交付申請の予約期間>2022年3月28日~遅くとも2023年2月28日*期限は4月28日の発表により今年9月末から2023年2月28日へと延長となりました。 予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合は、同日まで。(3)交付申請新築住宅の建築工事に着手し、出来高の工事完了の確認を持って「こどもみらい住宅支援事業」の補助金交付申請手続きをします。申請期間は、4月28日の発表により今年10月末から2023年3月31日まで延長となりました。交付申請の締め切りは、補助金を申請する人が多く予算上限に達すれば、2023年3月31日より早まる可能性もあります。(4)交付決定申請した内容が確認されたら、何も問題がなければ1ヶ月半〜2ヶ月ほどで交付が決定します。決定したら『交付決定通知書』というものが発行され、建築事業者の担当者にメールで通知されます。また、家を建てた建築主(お施主様)のもとにも交付決定を通知する書類が郵送されてきます。(5)補助金の確定・交付交付が決定した後は、対象となる補助金が家を建てた住宅会社の元へと振り込まれます。振込の時期は次の①②のいずれか。どちらか早い方になります。① 2022年10月末までに交付申請を行う場合、2022年度末(2023年3月末ごろ振込)、2022年11月以降に交付申請を行う場合、2023年度末(2024年3月末ごろ振込)② 完了報告の審査完了(当月20日締、翌月末支払予定)ここで気を付けておきたいのが、補助金は一旦建築工事を行なった会社の元に振り込まれる点です。還元方法は、最初に取り交わす「共同事業実施規約」で決めておくこととなりますので、しっかり内容を把握しておきましょう。(6)完了報告完了報告の期限までに新築住宅の引渡しと入居を受け、完了報告をすることとなります。戸建住宅の場合、完了報告の期限は4月28日の発表により2023年5月31日から2023年10月31日まで延長となりました。▶︎こどもみらい住宅支援事業のポイント こどもみらい住宅支援事業の予算額は542億円!2020年12月から約1年実施されていた「グリーン住宅ポイント制度」の予算額1,094億円と比べると、予算額が約半分ほど。そのため、申請したいと思っていても、タイミングを逃すと「予算がなくなって補助金が活用できない!」となる可能性があります。しかし、4月28日の発表により予算額は従来の予算額542億円に600億円追加され、総額1,142億円となりました。また、補助金を受けるためには、2022年10月31日までに契約・着工の後に交付申請を行うことが条件となっています。着工から交付申請までを今年10月31日までにしなければならないため、今からこの補助金を活用しようと思うと、意外と家づくりのスケジュールはタイトなものに。しかし、ここも4月28日の発表により、交付申請までの期限が2023年3月31日まで延長となりました。▶︎こどもみらい住宅支援事業2022年4月28日発表の交付申請期限等の延長2022年4月28日原油高・物価高騰による住宅価格上昇への対策として、子育て世帯等による省エネ住宅の購入支援等を継続的に実施するため、「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限を2023年3月31日まで延長することが国交省より発表されました。その内容は、次の通り。(1) 予算額の増額令和3年度補正予算542億円に加え、令和4年度予備費等において600億円を措置し、予算額が1,142億円に増額されました。(2) 契約期限・交付申請期限の変更変更前の契約期限・交付申請期限2022年10月31日が変更後2023年3月31日となりました。しかし、住宅・建築物のカーボンニュートラルに向けた取組を加速する観点から、より高い性能を有する省エネ住宅への支援に重点化するため、「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築については、2022年6月30日までに工事請負契約を締結したものに補助対象が限定されることになりました。(3) 完了報告期限の延長戸建住宅の変更前の完了報告期限2023年5月31日が変更後2023年10月31日となりました。以上、こどもみらい住宅支援事業vol.2として、手続きやポイント、更には4月28日の発表の交付申請期限等の延長について解説させていただきました。ご不明な点に関しては、気軽にお問い合わせください。*参考[事業公式サイト]こどもみらい住宅支援事業
こどもみらい住宅支援事業の予算額は542億円!2020年12月から約1年実施されていた「グリーン住宅ポイント制度」の予算額1,094億円と比べると、予算額が約半分ほど。そのため、申請したいと思っていても、タイミングを逃すと「予算がなくなって補助金が活用できない!」となる可能性があります。しかし、4月28日の発表により予算額は従来の予算額542億円に600億円追加され、総額1,142億円となりました。また、補助金を受けるためには、2022年10月31日までに契約・着工の後に交付申請を行うことが条件となっています。着工から交付申請までを今年10月31日までにしなければならないため、今からこの補助金を活用しようと思うと、意外と家づくりのスケジュールはタイトなものに。しかし、ここも4月28日の発表により、交付申請までの期限が2023年3月31日まで延長となりました。▶︎こどもみらい住宅支援事業2022年4月28日発表の交付申請期限等の延長2022年4月28日原油高・物価高騰による住宅価格上昇への対策として、子育て世帯等による省エネ住宅の購入支援等を継続的に実施するため、「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限を2023年3月31日まで延長することが国交省より発表されました。その内容は、次の通り。(1) 予算額の増額令和3年度補正予算542億円に加え、令和4年度予備費等において600億円を措置し、予算額が1,142億円に増額されました。(2) 契約期限・交付申請期限の変更変更前の契約期限・交付申請期限2022年10月31日が変更後2023年3月31日となりました。しかし、住宅・建築物のカーボンニュートラルに向けた取組を加速する観点から、より高い性能を有する省エネ住宅への支援に重点化するため、「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築については、2022年6月30日までに工事請負契約を締結したものに補助対象が限定されることになりました。(3) 完了報告期限の延長戸建住宅の変更前の完了報告期限2023年5月31日が変更後2023年10月31日となりました。以上、こどもみらい住宅支援事業vol.2として、手続きやポイント、更には4月28日の発表の交付申請期限等の延長について解説させていただきました。ご不明な点に関しては、気軽にお問い合わせください。*参考[事業公式サイト]こどもみらい住宅支援事業 -
ライフ・パートナーズ vol.62
- 投稿日


-
吹き抜けのメリット・デメリットについて徹底解説!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
吹き抜けのある家は開放感があり、憧れている人も多いのではないでしょうか。
オシャレな吹き抜けは人気の間取りで、いろいろなメリットがあります。
その反面、デメリットもあり、きちんと対策をしないと「こんなはずではなかった」と後悔することにも…。
ここでは、吹き抜けのメリットとデメリットにスポットを当て、失敗しないためのポイントを解説します!
注文住宅に吹き抜けを取り入れたいとお考えの方のご参考になれば幸いです。吹き抜けのメリット
主に一戸建ての玄関や階段、リビングなどに設けられることが多い吹き抜け。
その人気の理由はなんでしょうか?
吹き抜けのメリットについて、以下にピックアップしました!開放感バツグンでオシャレ
最上階の天井が見える吹き抜けは、空間が縦に広がり、とっても開放的!
広々と感じることができるため、狭い敷地に家を建てたい場合は特にオススメです。
また、吹き抜けがあるだけで素敵な間取りに見せてくれるメリットもあります。
吹き抜けの照明にこだわれば、グッとオシャレな空間に。
デザイン性の高さを感じさせるペンダントライトや、大人な雰囲気たっぷりのダウンライトなど、照明によってさまざまな雰囲気を演出できます。家の中が明るくなる
吹き抜けがあると、高い位置にある窓から太陽の光を取り込むことができるため、家の中が明るくなります。
特に、隣の家と間隔が近い場合は、どうしても日の光が遮られやすくなり、家の中が暗くなってしまうこともしばしば…。
しかし吹き抜けにして2階部分に窓をつけることで、1階まで採光が取れるようになります。
自然光が入りやすくなることで、日中に照明をつけることが減るため、電気代の節約にもなります。風通しがいい
暖かい空気は、下から上のほうに上がっていく性質があるため、縦に空間の広い吹き抜けがあることで、空気の循環が良くなります。
1階と2階に窓を設置すれば、下の窓から上の窓へと空気が流れ、うまく空気を循環させることができるのです。
風通しも良く、いつも家の中に新鮮な空気を入れることができるので、清々しさを感じながら生活することができますね。
また、天井に空気を攪拌するためのシーリングファンを設置することにより、部屋の空気を循環させることができるので、快適に過ごす家づくりが期待できます。家族とコミュニケーションが取りやすく
吹き抜けによって1階と2階が繋がり、家族同士のコミュニケーションが取りやすい環境になります。
例えば、ご飯の用意ができたことを2階にいる子供に伝える場合など、階段を上がって声をかけに行く必要はなく、1階から呼びかけることができます。
また、上下階の家族の気配を感じることができるので、家族同士のコミュニケーションを大事にしたい方や、幼い子どもの姿を視界に入れやすくしたい親世代には理想的な間取りと言えるでしょう。吹き抜けのデメリット
吹き抜けはオシャレで開放感があり、メリットがたくさんありますが、デメリットもあります。
家づくりで失敗を避けるには、しっかりデメリットを踏まえて、間取りを検討することが大切です。
以下でデメリットを解説します!光熱費がかさむ
吹き抜けは空間が縦に広いため、どうしても熱効率が悪くなってしまいます。
春や秋などエアコン不要の季節は、窓の開け閉めだけで温度調節ができるので快適ですが、エアコンが必要な季節には快適な温度になるまでに時間がかかることも。
特に吹き抜けが大きければ大きいほど、冷暖房の負荷は高くなり、
しかし、現在は家の性能が高く断熱性と気密性に優れた家が多く、そのため、一度暖められたり、冷やされるとそれが長持ちする傾向にあります。2階のスペースが狭くなる
吹き抜けの分、2階部分の床面積が狭くなるため、確保しておきたい部屋数や収納スペースに影響が出ることがあります。
あらかじめ何部屋欲しいか、収納スペースはどのくらい欲しいかを考えておき、バランスのいい間取りを検討することが大切です。耐震性が下がる可能性がある
地震大国である日本において、耐震性の強度は大きなチェックポイントです。
吹き抜けは空間が大きい分、柱や壁が少なくなるため、耐震強度が下がる可能性があります。音やにおいが気になる場合も
吹き抜けは、家族の気配を感じられることがメリットのひとつですが、その分、音やにおいが家全体に伝わりやすいため、どこにいても生活音が聞こえてしまいます。
「勉強に集中したい」「テレビの音が聞こえると気になる」など、プライバシーを確保したい場合にはあまりおススメできません。メンテナンスが大変
吹き抜けの2階部分に設置された窓や、吹き抜け天井に配置した照明器具などは、掃除やメンテナンスが大変です。また、クロスの張り替え時にも同様のことが言えます。
足場を組むか、高所専用の掃除道具で掃除する、または専門の業者に頼む、などの対応策が必要であり、費用が余計にかかることがあります。吹き抜けにする際に一番大切なこと
吹き抜けには、メリットもあればデメリットもあります。
吹き抜けを作るデメリットを踏まえ、後悔しない家づくりをするために一番大切なことはなんでしょうか?
それは、「吹き抜けを取り入れる目的を明確にする」ことです。
あなたが吹き抜けを取り入れることで最も求めていることは何でしょうか?
何を重視するのか明確にし、優先順位をつけることで家づくりの方針が定まります。
方針が定まるとプランの取捨選択に迷いがなくなり、結果的にあなたの意向に沿った満足のできる家づくりが叶うのです。
以下で、吹き抜けを取り入れる際の対策ポイントをご紹介しますので、 の 要素と照らし合わせながら、メリット・デメリットの理想的なバランスを考えてみましょう。吹き抜けの対策ポイント
吹き抜けによるデメリットの具体的な対策方法を解説します。
ポイントごとに解説しますので、参考にしてください。暑さ、寒さ対策
まずは、夏の暑さ、冬の寒さへの対策として、以下3つのポイントがあります。断熱性、気密性を高くする
夏の暑さ、冬の寒さの対策として、断熱性、気密性の高い住宅を作ることが大事です。・屋根や壁にしっかりと断熱材を入れる
・ペアガラスの断熱サッシを使う
・むやみに大きな窓は付けない上記のような対策を行うことで外からの暑さ寒さの侵入を防ぎ、断熱性を確保できます。
空気の循環を良くする
窓を高い位置につけると、空気が循環する上、採光もとれます。
窓を電動式で開閉できるようにすると、より便利でしょう。
吹き抜けの上部にエアコンや、シーリングファンを設置すれば、天井の空気を上手に循環させることができます。エアコン選び
吹き抜けに設置するエアコン選びは、重要な要素のひとつです。
エアコンを選ぶポイントとして、対応する畳数が実際よりも上のエアコンを選ぶことが大切。
通常のエアコンの他に、床下エアコンや床暖房を導入する選択肢もあります。
足元から、効率的に部屋を暖めてくれるのでオススメです。音、プライバシー対策
プライバシーの確保は、個室を作ることで解決されます。
「家族とシェアする空間」と「プライベートの空間」が両立する家を目指しましょう。
「個室は作りたいけど、家族のつながりも重視したい」という場合は、 を作り、小さな窓を設けるのがオススメ。
窓を開ければ1階の家族と容易にコミュニケーションがとれます。耐震リスク対策
吹き抜けを作ることによる耐震強度の低下は、建築方法や技術によって回避することができます。
柱や梁を見せる設計にするなど、いろいろな方法がありますが、何よりも信頼できるハウスメーカーを選ぶことが大切。
しっかりと相談に乗ってもらいましょう。狭さ対策
「吹き抜けにしたいけど狭くなるのもイヤ!」という方はスキップフロアにすることをオススメします。
スキップフロアとは、1つの階層に複数の高さのフロアが設けられた間取りのこと。
1階と2階をつなぐ階段をそのまま吹き抜けにし、リビング階段とスキップフロアを組み込めば、有効的に使える空間が広がるうえ、縦空間のつながりにより開放感がかなえられます。まとめ
吹き抜けのある家は、明るく開放的で、風通しが良いというメリットがありますが、その反面デメリットもあります。
ご自身の目的に沿って家づくりをすることが大切です。いろいろと迷うことも多い家づくり。
その不安を解消できるよう、丁寧にカウンセリングを行い、満足のできる家づくりができるよう全力でサポートさせていただきます。
吹き抜けのある注文住宅をご検討されているお客様は、ぜひお問い合わせください。 -
寝室のクロスは何色にする? みんなのクロス選びから参考にしてみよう◎
- 投稿日
こんにちは!名稲建設株式会社です。
1日の中でも過ごす時間が長い場所といえば……寝室です。1日8時間寝るとしたら、1日のなんと1/3を寝室で過ごしているということに。
だからこそ、心地よく眠れる寝室を家づくりでもこだわってみてはいかがでしょうか?今日はくつろいで過ごしたい寝室のクロス選びのアイデアをお客様邸からご紹介いたします。
▶︎落ち着きを演出するグレーのクロス

1日の疲れを癒す睡眠時間。ぐっすりと眠るには、やっぱり寝室も落ち着いた雰囲気にしておくことが大切です。
寝室に使うクロスは、ビビッドなビタミンカラーなどにするよりも、グレーやネイビーなどの色がおすすめ。こちらのお客様邸でも、グレーのクロスを採用されています。
朝目覚めた時に、明るい気持ちで目覚めたい!という方は、クロスを白にするのも良いでしょう。
床の色に合わせて、ベッドのヘッドボード側だけアクセントにグレージュカラーを取り入れれば、明るさもキープしつつ落ち着いた雰囲気に。
また、寝室にプロジェクターなどを投影したい場合には、黒っぽい壁よりも映像がきれいに映る白がおすすめ。最近人気のプロジェクター一体型の照明などを検討されている場合には、クロスの色選びの際にも、気をつけましょう。
こちらのお客様邸では、ライトを消すと、時計が投影されるようになっていてとってもおしゃれです!今回は、ちょっぴり落ち着きある雰囲気のクロスの事例をご紹介しましたが、寝室は来客に見られない場所だからこそ「遊び心を取り入れたい!」と考えるのももちろんOK♪
世界に一つだけの注文住宅を作るからこそ、マイホームのクロス選びも楽しんでみてくださいね◎ -
人気の収納スタイル!「ウォークインタイプのシューズクローク」の魅力とは?
- 投稿日
こんにちは!名稲建設株式会社です。
家の中で散らかりやすい場所といえば、玄関です。家族の人数が増えれば増えるほど、靴の数もたくさんに!靴だけでなく、傘やベビーカー、アウトドアグッズなどなど、意外と玄関に置くものは多いもの。
とは言え、すっきり綺麗な玄関を保つのは習慣が大切。「ただいま!」と帰宅して靴を脱ぎっぱなしにしている子供に「片づけなさい!」と怒るのも、結構ストレスですよね。
そこで今日は、努力しなくてもきれいな玄関がキープできる人気の玄関収納スタイルをご紹介いたします◎▶︎玄関収納はウォークインタイプがおすすめ!

例えば、あるお客様邸の玄関収納は、玄関を開けて右手側に大きな土間収納が。
家族が多いこちらのお客様。その分シューズクロークも大容量にしています。天井いっぱいのオープン収納棚を作ることで、靴以外にもお子様の部活道具やアウトドア用品がたっぷりしまえます。
また、土間空間も自転車が入れられるよう大きさをしっかりと計算しています。
明るいイエローのクロスがおしゃれなこちらのお家は、玄関の土間空間をL字型に。広さを感じられる玄関になっています。一見シンプルな玄関のように見えますが、土間空間から白いドアを開けると……。

家族用のシューズクロークに土間がつながっています。
ウォークスルータイプの玄関収納は、来客に脱ぎっぱなしの靴を見せたくない!という方にピッタリ。
いつでもきれいな玄関で、お客さまをお出迎えできます。少しでも片付け楽で暮らしやすいマイホームにしたいとお思いの方は、気軽にご相談くださいね!
-
ライフ・パートナーズ vol.61
- 投稿日


-
間取りの新定番!ファミリークローゼットとは?
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
家事に子育て、仕事、毎日大忙しの共働き世代。
「気づけば家の中がぐちゃぐちゃ…」「片付ける時間も余裕もない!」という方も多いのではないでしょうか。
注文住宅を建てるなら、オシャレで住み心地の良い家にしたいもの。
少しの時間や労力できれいに片付けられる、動線の良い家を作りたいですよね。
そんな共働き世帯に特に注目されている「ファミリークローゼット」は、家事や生活動線をコンパクトにしてくれる収納として人気を集めています。
暮らしやすい注文住宅を建てたい方に、ファミリークローゼットを取り入れたオススメの間取りや失敗しないためのポイントまで解説します!ファミリークローゼットとは?
時短や動線の簡素化に威力を発揮するファミリークローゼット。
ここでは、「ファミリークローゼットってどんなもの?」「どんなメリットがあるの?」といった疑問にお答えします!ファミリークローゼットについて
ファミリークローゼットとは、その名の通り「家族全員で使うクローゼット」のこと。
クローゼットといえば各々の部屋に設けるのが一般的ですよね。
ファミリークローゼットは、1ヵ所の収納スペースに家族全員の衣類などをまとめて収納できるような、大きなサイズの収納です。
収納だけでなく、ファミリークローゼットの中に着替えスペースを作ったり、アイロン台を設置したりと、収納の役割を超えて幅広く活用することもできます。ファミリークローゼットのメリット
ファミリークローゼットは収納場所を1ヵ所にまとめられるので、生活動線や家事動線をコンパクトにすることができます。
動線を効率的にすることで、家事の負担を軽減できたり、効率的に日常生活を送れたりと、無駄な動きの少ない理想的な間取りにすることができるのです。
また、部屋が散らかりにくくなることもメリット。
動線がコンパクトになるため、畳んだ後の洗濯ものや帰宅後のカバンなどの「とりあえず置き」を避けることができます。
いつも整理整頓されたきれいな部屋をキープすることができるのですから、大助かりですね!ファミリークローゼットのタイプ
ファミリークローゼットの動線タイプは、「ウォークインタイプ」と「ウォークスルータイプ」があります。
「ウォークイン」と「ウォークスルー」の明確な違いは、収納の中を通り抜けられるか、通り抜けられないか、ウォークインは収納の中を歩き回れて、ウォークスルーは入口を2ヵ所以上設け、部屋から部屋へ移動が出来ます。・ウォークインタイプ
出入口が1ヵ所の物置タイプ。
ウォークスルータイプよりも収納力があります。・ウォークスルータイプ
出入口が2ヵ所以上あり、クローゼットを通り抜けることができるタイプ。
行き止まりがないため回遊性があり、ストレスのない家事動線・生活動線を作ることができます。
しかし、クローゼット全体の広さが同じの場合、人が通るためのスペースが必要になるため、ウォークインタイプより収納力が少し落ちます。
どちらのタイプにするかは、間取りや用途に応じて、使いやすいタイプを選びましょう。ファミリークローゼットを取り入れたオススメの間取り
ファミリークローゼットは、どこに配置すると便利でしょうか?
ここではオススメの間取りをご紹介します!ランドリールームの近く
ランドリールームの近くにファミリークローゼットを配置すると、洗濯から収納までの流れがスムーズになります。
洗濯物を屋外に干したい場合、ファミリークローゼットをウォークスルータイプにして、屋外の洗濯物干し場と繋げるのがオススメ。
「洗濯する」「干す」「畳む」「収納する」の一連の流れを一気に行うことができ、洗濯の動線が短縮されます。
畳んだ後の洗濯物を各部屋に運ばなくてよいので、とっても便利ですね!
ファミリークローゼットに、帽子やバッグ、タオルなども収納し、お着替えルーム兼用にするのも◎。
整理整頓もしやすくなるうえ、朝の支度やお風呂の時など、着替えを自分の部屋に取りに行く手間がなくなり、とっても便利です。玄関の近く
玄関に繋がる形でファミリークローゼットを設けると、外出時や帰宅時に便利です。
帰宅時は、「靴を収納」「上着、帽子、マフラーをかける」「カバンを置く」という流れを最短で完了させることができます。
「自分の部屋に行く前に一旦カバンをリビングに置いておこう」というような「とりあえず置き」を回避でき、リビングが散らかりにくくなります。
ファミリークローゼットに普段着や制服も収納しておけば、更に便利!
外出時は、自分の部屋に戻ることなく1ヵ所で支度を終えることができます。リビングの近く
家族が長時間くつろぐ場所であるリビング。のんびり過ごしたいからこそ各々持ち込みたいものもありますよね。
リビングの横にファミリークローゼットを設置すれば、わざわざ自分の部屋に物を取りに行く必要がなくなるので、使い勝手がアップします。
片付けやすくなるので、「リビングに物を置きっぱなし」という事態を避けることができ、リビングをきれいにキープすることにもつながるでしょう。
また、リビングの利便性がアップすることにより、家族がリビングにいる時間も増え、コミュニケーションを取る時間が増えることも期待できます。失敗しない!ファミリークローゼットのポイント
収納力があり、便利なファミリークローゼット。しかし、「作って後悔した」という方も少なからずいるようです。
失敗の原因や、失敗を避けるためのポイントも合わせて解説します。ありがちな失敗と原因
ファミリークローゼットでよくある失敗は、以下のようなものです。・使うのに不便な場所に作ってしまった
・大容量すぎて整理整頓できず、物の場所が分からなくなった
・ファミリークローゼットが狭すぎた
・ファミリークローゼットが大きすぎて、生活スペースが狭くなってしまったファミリークローゼットを導入するには、次のポイントを抑えることが大切です。
失敗を回避するためのポイント
ファミリークローゼットを作るときは、「何を収納するか」「どんな使い方をするか」を具体的にシミュレーションすることが大切。
使い方や収納物によって、ファミリークローゼットの最適な間取りや広さが決まるからです。
さらに、収納物のジャンルは絞るのがマスト。
あれもこれもと収納ジャンルを広げすぎると、「どこに何があるのか分からない」「欲しいものがすぐに取り出せない」ということになりがちです。
使いやすいファミリークローゼットにするために、具体的に使い方や収納するものを絞り込みながら検討しましょう。
検討する際は、現在の家族の様子だけでなく、「将来は家族が増えるかも?」「子どもが大きくなったら、自分の荷物は自分で管理したいかな?」など、将来の姿もイメージすると更に良いですね。まとめ
いかがでしたか?
家事の負担減や日常生活の時短に繋がるファミリークローゼット。
上手に設置するには、具体的に使い方や収納するものをイメージすることが大切です。
イメージが固まったら、ハウスメーカーにしっかり伝えることをオススメします。
予算含め、バランスの良いベストな間取りを提案してくれることでしょう。 -
【保存版】注文住宅 ご相談から引き渡しまでの流れをご紹介
- 投稿日

注文住宅を建てるまでは、どのような流れになるのでしょうか。
「注文住宅はどのような流れで建てるのか」
「どれだけの期間がかかるのか」
「ハウスメーカーや工務店はどう選ぶのか」
「建築代金の支払いの仕組みはどうなっているのか」今回は、このような悩みを解決できるような内容を紹介していきます。
この記事を読むことで、以下の内容が理解できます。
・注文住宅のご相談から引き渡しまでの期間及び流れ
・ハウスメーカーや工務店の選び方
・建築代金の支払い方法注文住宅のご相談から引き渡しまでの期間及び流れ
・ご相談~設計プランの提案~ご契約:2ヶ月~3ヶ月(土地が購入がない場合、1ヶ月程度で土地が決った場合)
・ご契約~インテリア打ち合わせ~着工:2ヶ月~3ヶ月
・着工~引き渡し:建物の規模・建築条件にもよりますが4ヶ月~5カ月注文住宅の相談から引き渡しまでにかかる期間は、約1年が一般的ですが、設計プランやインテリアプランにこだわりたいという方は、その分打ち合わせ回数が増え、打ち合わせから着工迄の期間が伸び、トータルの期間が伸びることになります。また、延床面積が標準よりも大きい注文住宅の場合、着工から引き渡し迄の期間が伸び、同じようにトータルの期間が伸びます。
引き渡し・入居のご希望の時期がある方は、早めに相談されることをおすすめします。ご相談
・資金計画やプランニング
・ご入居までのスケジュールご相談の段階では、資金計画やプランニング、全体のスケジュールについて、打ち合わせします。プラス重要なのが、「どこに建てるか」という点、希望の土地を見つけるまでに6ヶ月以上、ときには数年かける人もいます。
注文住宅には、住宅を建てる本体工事費用だけでなく、給排水設備などの付帯工事費用、その他の諸経費がかかります。
工事分類
内容
総予算に対する割合
本体工事費用
基礎・構造・設備工事
75~80%
付帯工事費用
ガス・給排水・外構工事
15~20%
諸経費
申請費用・税金
5~10%
参考:注文住宅の費用や相場 大工が教える失敗しない家づくり(https://ie-daiku.org/souhiyou.html)
それぞれの内訳は上記のようになっているので、計画している総予算をこの割合で振り分けて、計画そのものに妥当性があるかどうかを計算してみてください。
例えば、岐阜県の注文住宅の相場は約3,228万円(建物のみ)です。
・本体工事費用(総予算の80%の場合):約2,582万円
・付帯工事費用(総予算の15%の場合):約484万円
・諸経費(総予算の5%の場合):約161万円それぞれの費用に振り分けてみると上記のようになります。
費用の目安として参考にしてみてください。参考:岐阜の注文住宅相場(https://www.housingexhall.com/knowledge/gihu-homeprices.html)
また、住宅ローンの借入額は各金融機関の住宅ローンシミュレーションツールで簡単に調べられるので、予算の参考にすることをおすすめします。
参考:住宅ローンシミュレーション(https://loan.mamoris.jp/)
土地探し
・土地を所有していない場合は土地探し土地探しは一般的に不動産会社へ相談し、希望の立地かつ予算に合う土地を探します。
通勤や通学にかかる時間、スーパーや病院などの周辺環境や日当りの良さ、災害危険区域に入っていないかなど、土地を決める上で検討すべきことはたくさんあります。
ハウスメーカーや工務店によっては土地探しも一緒にしてくれることがあるので、相談してみてください。参考:国土交通省 標準値・基準値検索システム(https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)
敷地(地盤)調査
・敷地状況の確認
・地盤調査
・法的規制の調査
・電気、ガス、水道施設敷地調査では、その土地にどのような注文住宅が建てられるかの現地調査を行います。
地盤調査結果によっては、地盤改良が必要になることがあります。・敷地やその周辺が埋め立て土地や盛り土で造成された土地
・過去に陥没があった土地、液状化や不同沈下の可能性がある土地など総合的な周辺情報により地盤の強化を要すると判断された場合は、地盤改良工事を実施します。
設計プランの提案・住宅ローン事前審査
・オリジナルプランのご提案
・仕様・設備・建築費などの打ち合わせ
・住宅ローン事前審査申し込み設計プランの提案では、ハウスメーカーや工務店のオリジナルプラン提案、仕様や設備・建築費を打ち合わせします。
設計プランでは、どのような注文住宅にしたいのか、しっかりとイメージを決めておくことが大切です。
「吹き抜けがほしい」「1階に和室を入れたい」など絶対に外せない条件は、優先順位をつけてメモしておきましょう。
また、家族の将来を見据えた間取りにすることも大切です。
老後生活でも使いやすい間取り、こどもが成長しても十分な収納など、一生モノの注文住宅だからこそ、生涯使える間取りを考えましょう。ご契約・住宅ローン本審査
・建築工事請負契約のご締結
・市や民間機関への建築確認申請
・注文住宅完成までのスケジュールのお渡し
・契約金、諸費用のご入金
・住宅ローン本審査申し込み設計プランが決まれば、工事請負契約をします。
また、このタイミングで住宅ローンの本審査申し込みをします。
工事請負契約を締結した後にプランを変更しようとすると、変更契約を結ばなければなりません。
変更契約には追加費用がかかる他、建築確認申請の後からでは変更できない項目もあるので、担当のハウスメーカーや工務店に確認しておきましょう。インテリアプランの打ち合わせ
・インテリアプランの打ち合わせ
・ご契約内容の確定インテリアプランを打ち合わせし、契約内容を確定させます。
設計プランで決めた間取りに加えて、家具の配置や窓の大きさなどの詳細を決めます。着工
・着工立ち会い
・着工金のご入金
・建物配置の確認立ち会い
・地鎮祭
・近隣挨拶
・打ち合わせで確定した内容で工事が始まります。着工前には、着工金の入金や地鎮祭、近隣挨拶を行いますが、「地鎮祭はしない」「近隣挨拶は現場監督に任せる」という方もいます。
着工したら工事の様子を見に行けるので、気になって毎日見に行くという方もいます。
ただし、様子を見に行くときは工事の邪魔にならないように注意してください。上棟
・上棟立ち合い
・上棟式
・中間金のご入金上棟とは、住宅の建築において、柱や梁など建物の基本構造が完成し、家の最上部で支える棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付けることを指します。
上棟式は、施主と工事を担当する大工さんや職人さん、工事関係者で行う式で、建物が無事に完成することを願うことを前提として、施主側と大工側の親睦を深めるためのきっかけとして行います。上棟式では塩やお神酒、米、おもてなしの料理や飲み物などを施主側が用意しますが、上棟式を行う行わないは、ハウスメーカーに一度確認をとってみましょう。竣工・検査
・竣工立ち会い
・引き渡しについて説明
・建物表示保存登記など各種書類手続き注文住宅が完成したら、完了検査の後に検査済証の発行を受けます。
また、竣工立ち会いの際には、完成した注文住宅に傷や汚れがないことを確認します。
竣工立ち会いで気になった部分で修正可能なところは、修正をお願いできるのでしっかりチェックしましょう。引き渡し
・最終金のご入金
・建物お引き渡し式
・各種設備取扱説明
・新居の鍵、保証書のお渡し最終金の入金、引き渡し式、各種設備取扱説明が終わったら、ついに引き渡しとなります。
ハウスメーカーや工務店の選び方
ここでは、自分にあったハウスメーカーや工務店の選び方について説明していきます。
品質の良さ
品質が良く、住みやすい注文住宅を建ててくれる建築会社を選びましょう。
建築事例を参考にしたり、モデルハウスを見学させてもらったりして確認するようにしましょう。提案力があるか
希望の条件を反映したプランを提案してくれる建築会社を選びましょう。
ただ希望の条件を汲み取ってくれるだけでなく、より使いやすいプランなどのさらなる提案をしてくれる建築会社は提案力があると言えます。予算内に収まるか
希望の条件を出して、できるだけ予算内に収めてくれる建築会社を選びましょう。
予算をオーバーしていたとしても、将来的に見ればコストをかけておいた方がメリットがある素材もあるので、予算オーバーしたからといって悪い建築会社だと決めつけないようにしましょう。担当者と合うか
担当者との相性も重要な要素です。
担当者の知識だけでなく、話が合うか、コミュニケーションが取りやすいかなど、スムーズに話が進まなければ理想の注文住宅が建てられません。注文住宅の支払い方法は?
ここでは、注文住宅の支払い方法について詳しく説明していきます。
3~4回に分割して支払う
一般的な注文住宅の場合、建築費用の支払いは3〜4回に分割して行います。
・工事請負契約時:建築費用の10%
・着工時(着工金):建築費用の30%
・上棟時(中間金):建築費用の30%
・引き渡し時:建築費用の残代金注文住宅を建てるときには、支払いのタイミングや計画についてしっかり説明してくれるハウスメーカーや工務店を選ぶようにしましょう。
住宅ローン審査の流れ
住宅ローンの審査は、「事前審査→本審査」という流れです。
計画段階で事前審査を受けておくことで、どのくらい借り入れできるかの目安が分かります。事前審査は、購入の申込をしていない検討中の土地で審査してもらうことも可能です。
事前審査が通り、建築工事請負契約を結んだ後に行うのが本審査です。事前審査とは異なり、より多くの情報をもとに審査が行われます。事前審査の内容に加えて物件の担保評価や物件瑕疵はないか、取引関係人に反社会的勢力はいないかなど、住宅ローン利用者から提出される各種書類をもとに審査が行われます。一般的に1週間から2週間程度審査に時間がかかります。つなぎ融資
つなぎ融資は住宅ローンを前借りする形で利用できるサービスで、住宅ローンの実行時期が引き渡し時の場合、それまでにかかる費用にあてることができます。つなぎ融資の期間は金利だけを支払い、注文住宅が完成すると同時に住宅ローンと一本化されます。
つなぎ融資は、住宅ローンと比べて金利が高く設定されているという特徴があります。
そのため、つなぎ融資は住宅ローンの融資実行時に一括返済しますが、つなぎ融資の完済までの期間は利息を支払う必要があり、期間が長ければ利息の負担が大きくなることを理解しておかなくてはなりません。なお、住宅ローンの実行時期が中間金支払い時という金融機関の場合には、つなぎ融資は不要になります。その他、土地の代金及び建物の代金をそれぞれ一つずつ住宅ローン契約することが出来る金融機関もあります。
※ハウスメーカーや金融機関によっては、つなぎ融資が利用できないことがあるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は注文住宅のご相談から引き渡しまでの流れを紹介しました。
注文住宅の引き渡しまでをスムーズに進めるためにも、全体の流れをイメージしておくことが大切です。
今回紹介した流れや支払い方法を参考にして、納得のいく注文住宅を建てられれば幸いです。 -
ライフ・パートナーズ Vol.60
- 投稿日


-
注文住宅 予算オーバーにならないために
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
注文住宅を建てるときに陥りがちなのが、想定していた予算よりも費用がオーバーしてしまうことです。
高性能なキッチンなどの設備、おしゃれで高級な床材や建具、子どもたちが遊べる庭など希望の条件をどんどん入れていくと、予算オーバーになるのはよくあることです。
今回は、注文住宅で予算オーバーにならないために気を付けることについて解説していきます。「理想の注文住宅を建てたいけど、予算オーバーを防ぎたい」
という方は必見の内容になっているので、ぜひご一読ください。
注文住宅で予算オーバーになる原因とは
・設備や構造にこだわりが多すぎる
・補助金制度を利用していない
・諸費用・付帯工事を考慮していない注文住宅で予算オーバーになる原因には、上記3つが挙げられます。
設備や構造にこだわりが多すぎる
設備や構造にこだわりすぎると、予算オーバーになりがちです。
ウッドデッキ、特徴的な屋根や家の形、ダウンライト、高性能なキッチンなど注文住宅はこだわろうと思えばいくらでもこだわれます。
そこで、自分たちの要望をすべて通そうとすると、必然的に予算オーバーしてしまいます。補助金制度を利用していない
・こどもみらい住宅支援事業
・地域型グリーン化事業
・自治体からの補助金注文住宅を建てるときに利用できる補助金制度はいくつもあります。
例えば、「こどもみらい住宅支援事業」は、子育て支援を目的とした住宅補助金制度です。
子育て世帯や若者夫婦世帯を対象としており、省エネ性能の高い住宅を新築するか、省エネ性能の高い住宅にリフォームすることで、補助金を受給できます。「こどもみらい住宅支援事業」について、もっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください!
「こどもみらい住宅支援事業」について解説します!–名稲建設株式会社(https://meito-fuso.com/column/kodomomirai/)
補助金を受給できれば、注文住宅のグレードをワンランクアップさせることも可能ですので、受給可能な補助金制度を調べて、検討してみることをおすすめします。
諸経費・付帯工事を考慮していない
工事分類
内容
総予算に対する割合
本体工事費用
基礎・構造・設備工事
75~80%
付帯工事費用
ガス・給排水・外構工事
15~20%
諸経費
申請費用・税金
5~7%
注文住宅の費用や相場 大工が教える失敗しない家づくり(https://ie-daiku.org/souhiyou.html)
注文住宅に限らず、住宅を購入する際には本体工事費用と別に、付帯工事費用、諸経費がかかります。
それぞれ費用の相場は上記のようになっています。
注文住宅を建てるために当てられる本体工事費用は、総予算の75~80%となっているので、予算全てを注文住宅に当てられると考えてはいけません。注文住宅の予算を削る方法6選
この項目では、注文住宅の予算を削る方法6選をご紹介します。
延床面積をできるだけ小さくする
注文住宅は一般的に「床面積×坪単価」で建築費用が計算されます。
坪単価とは家を建てるときの1坪(タタミ2枚分/およそ3.3㎡)あたりの建築費のことです。坪単価が50万円の住宅メーカーの場合、床面積40坪の注文住宅を建てるなら
40坪×50万円=2,000万円床面積を減らし35坪の注文住宅を建てるなら
35坪×50万円=1,750万円
になります。床面積を5坪(約16.5㎡)減らすだけで、250万円のコストダウンです。
自分たちの生活スタイルにあったちょうどいい広さなのか、もう1度検討することをおすすめします。間取りを見直す
・部屋・窓の数を減らす
・和室を作らない
・間仕切りを減らす
・バルコニーを必要以上に大きくしない
・部屋を本当に必要な広さにする
・収納スペースをまとめる間取りだけで、これだけの見直しポイントがあります。
こども部屋の間仕切り壁をなくしたり収納スペースをまとめたりと、必要のない余計な空間を作らない、まとめられるものはまとめることが予算オーバーを抑えるコツです。水回りの設備は1カ所・1つの階にまとめる
トイレ、キッチン、お風呂など水回りの設備は、1カ所、1つの階にまとめるようにしましょう。
1つの階にまとめることで配管が長くならず、前述した付帯工事費を抑えられます。
トイレを1階にも2階にも設置したい場合は、2階のトイレを1階の真上にすると、配管の長さを節約できます。建材や設備のグレードを落とす
注文住宅を建てるとき、最新式のキッチン、太陽光発電パネルや無垢材など、高機能高品質な設備や素材のカタログを見ているとワクワクしますよね。
ですが、注文住宅では、素材や設備のグレードを上げすぎてしまい予算オーバーになることが多いです。
システムキッチンでは、建築会社標準仕様のキッチンを選択すれば追加費用はかかりませんが、グレードを上げるとなるとオプションでの対応になることが多いので、高いもので200万円以上の追加費用がかかります。
キッチンのこだわりを捨てて、標準仕様のものにすれば、約200万円のコストダウンになることがわかります。
高級なシステムキッチンなど、グレードの高い設備が本当に必要なのかをよく考えると、予算オーバーを防ぐことに繋がります。予算オーバーしないで後悔のない注文住宅を建てるためには
・こだわりの優先順位をつける
・予算はオーバーするものと考えるこの項目では、予算オーバーしないで後悔のない注文住宅を建てるために必要な上記2つのポイントについて、解説していきます。
こだわりの優先順位をつける
注文住宅の予算オーバーを防ぐためには、よほどの予算がない限り、希望条件のどれかを削らなければなりません。
・全体から決め、細部は後回しにする
・設備の使用頻度は高いのか
・将来的に不便にならないか上記のようなルール決めをしておくことで、優先順位をつけやすくなります。
注文住宅の細部は後からでも変更できることが多いため、予算オーバーになったときにも調整が可能です。注文住宅のプランは全体から決めていきましょう。
また、希望の設備の使用頻度は高いのかをよく考え、その設備が本当に必要なのか十分に吟味する必要があります。
出産や老後のことを考えて、注文住宅を建てることも重要です。
3階建ての注文住宅や、勾配のきつい階段にしてしまったせいで老後に不便になってしまった、ということにはなりたくありませんよね。
注文住宅で予算オーバーしたときは、将来のことを考えたときに削れるポイントがないのかを考えてみてください。予算はオーバーするものと考える
そもそも、注文住宅の予算はオーバーするものと考えるようにしましょう。
理想の注文住宅を建てようと思うと、追加の設備や間取りによって費用はどんどんかさんでいきます。
そのため、2000万円の予算にするなら2200万円用意するなど、予算の+10%を用意しておくことで予算オーバーに余裕を持って対処できます。まとめ
今回は、注文住宅で予算オーバーにならないためのポイントを紹介してきました。
1生に1度の機会かもしれない注文住宅に、理想を詰め込みたいという気持ちはわかります。
優先順位のルール決めをしっかり行い、後悔のない注文住宅を建てられるようにしましょう。
名稲建設株式会社では、予算内で最善の提案ができるように努めています。一緒に理想のマイホームを検討しましょう。